生産管理とは?仕事内容や課題、効率化のポイントをわかりやすく解説
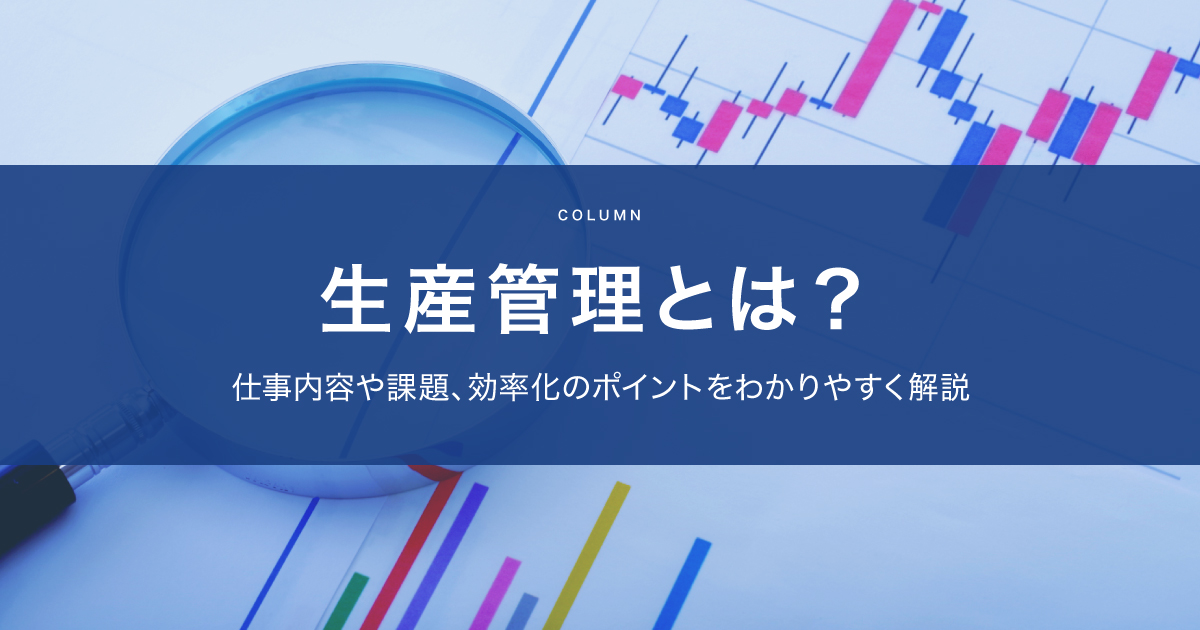
製造業における生産管理とは、計画に沿って生産業務全体を管理することです。受注や需要に対して自社製品を効率よく生産し、利益を最大化させるためには、適切な生産管理が欠かせません。この記事では、生産管理の目的や詳しい仕事内容、企業が抱えやすい課題について解説します。効率化におすすめの生産管理システムについてもご紹介しますので、参考にしてください。
生産管理とは?

生産管理は、生産活動を最適化するために重要な業務です。生産管理とはどのような仕事を指すのか、まずはその目的と重要性について分かりやすく解説します。
生産管理の基礎知識。役割や重要性
製造業における生産管理とは、生産計画に沿って生産業務全体を適切に管理することです。適切に管理することで効率的な生産体制を確保し、利益の最大化を図ります。
そもそも生産業務は、具体的な計画や指示に基づいて行うのが一般的です。これを管理するのが生産管理業務であり、その内容は多岐にわたります。具体的には、需要予測から始まり、生産計画の立案や調達・購買計画、品質管理や工程管理などを行って、適切にモノづくりの現場をコントロールするのです。
非常に重要な業務であることから、生産管理部門を設けて生産管理を行っている製造業も多くあります。
生産管理を行う目的
製造業において、生産管理を行う主な目的は次のとおりです。
- 効率的な生産体制の確保
- 品質の確保
- 納期の遵守
- コスト削減
- 資源の最適化
上記の目標を達成するための重要な指標として、「QCD(Quality・Cost・Delivery)」という3つの要素が知られています。
- 品質(Quality)
- 原価(Cost)
- 納期(Delivery)
3要素「QCD」はバランスよく管理することが大切です。例えば、高い品質の製品を作ったとしても原価が必要以上に掛かったり、納期に遅れたりしては、顧客の要求を満たしているとは言えません。逆に、低コストで納期に遅れることなく納品できたとしても品質が低ければ、その場合も顧客は納得しないでしょう。
生産管理の目的を果たすための役割として、QCDの最適化が重要です。それが顧客の信頼と満足を得て、業績アップにもつながるのです。
生産管理の仕事内容
先述したように、生産管理の仕事は数多くあります。それぞれの内容を詳しく見ていきましょう。
受注管理(需要予測)
受注管理(需要予測)とは、自社製品の受注量を予測することです。過去の受注データや販売計画、競合他社の状況、景気、社会動向といった情報を多様な角度から調査して、市場における自社製品の需要を分析します。
特に受注生産を行っている場合、受注管理は欠かせません。コストを意識しながら納期に間に合うよう生産量を確保する必要があるためです。
見込生産においても、需要が供給を上回れば欠品し、需要が供給を上回れば過剰在庫となってしまいます。どちらにしても予測が正しく行われなければ、利益は上がらないのです。
生産計画の立案と調整
需要予測や受注状況を考慮して、生産計画を立案します。生産に必要な資材の量、設備、人員の配置などを整理し、「なにを、いつまでに、いくつ」作るのかコストも考慮しながら計画します。
製品によっては、新たな生産ラインの立ち上げが必要になることもあるでしょう。その場合は新製品の製造に対する準備期間など、あらゆる情報を整理します。自社にどれくらいの生産能力があり、どのくらい供給できるのか、スケジュールと合わせて調整します。
【関連記事】生産計画とは?生産性を高める「立て方のコツ」やシステム・ツール活用法を紹介
調達・購買の計画
生産計画が整ったら、製造するために必要な部品や材料などを調達します。ここで大切なのがスケジュールに見合った調達計画を立てることです。生産計画や納期、コストに合わせ、各工程が滞りなく進められるようにします。
調達が遅れると製造がストップします。逆に過剰に調達してしまうと、資材の過剰在庫となりキャッシュフローに悪影響を及ぼします。最適な量と時期を見極めることが肝要です。
在庫管理
調達した部品や材料は、適切な在庫管理が必要になります。出荷スケジュールを遅らせないためには、部品や材料といった資材だけでなく、仕掛品や完成品の在庫管理も欠かせません。「なにが、どこに、どれくらい」あるのか、正確な在庫状況を把握します。
工程管理
製品づくりにおいては、製造過程の作業を分類化・体系化した「工程」があります。生産活動全体を計画・調整・監視することに焦点を置いた生産管理に対し、工程管理では工程ごとに効率的な作業手順を計画したうえで指示を出し、進捗や設備の負荷状況、工程納期を管理します。
各工程を管理し、全体的なスケジュールが遅れることなく進められ、納期に間に合うようにしていきます。
【関連記事】工程管理とは?システム・ツール活用術や課題解決のポイントを解説
品質管理
品質管理は、品質基準や規格に基づき、製品の品質を確保するために行います。完成品はもちろんのこと、資材や仕掛品の品質管理も必要です。品質管理業務には、検査や不良品対応、不良品の改善に対する活動も含まれます。
また、トレーサビリティの管理も重要です。製造業におけるトレーサビリティとは、製品に使われる資材などの調達をはじめ、生産、流通、販売などの各工程で仕入れ先や作業者を記録し、追跡可能な状態にすることを指します。
不良品などトラブルが発生した際は、シリアルナンバーやロットナンバー、各種伝票番号から製品を特定し、トラブル対応します。品質管理を怠ると顧客の信頼喪失にもつながるため、重要度の高い業務の一つと言えるでしょう。
【関連記事】品質管理とは?品質保証との違いや実践で役立つ9つの手法をくわしく解説
コスト管理(原価管理)
生産活動にかかるコストを把握し、コスト削減や効率化のための施策を検討します。事前に算出した標準原価と実際にかかった実施原価を比較、分析することでコスト削減を目指します。
コスト管理では、原材料や部品などの資材、人件費、資源(光熱費など)、設備費などについても検討していきます。
外注管理
製造するにあたり、全ての工程を自社で行うのではなく、外注することがある場合は、外注管理も必要です。外注先の選定にはじまり、作業進捗の管理、資材や完成品の品質チェックなど、管理すべき項目は多岐にわたります。
自社での工程が滞りなく進められても、外注で遅れが出たために納期遅れとなることもあります。外部との細やかなコミュニケーションが必要になるでしょう。
関連部門との連携
製品を完成させるためには、生産管理部門だけでなく、部門を越えた連携も重要となるでしょう。部門間で意見が食い違い、対立してしまっては良い結果が得られません。生産現場はもちろん、購買、財務、営業などの関連部門と密なミュニケーションを図り、協力して生産活動を推進することが重要です。
生産データの分析
生産活動に関するあらゆるデータを収集・分析し、生産効率や品質の改善ポイントを確認することも大切な業務です。近年では、IoTやAIの活用によってデジタル化が進む一方で、データを十分に活かせていない企業も多いのではないでしょうか。
生産データの分析手法として、例えば、PDCAサイクルを回したり、データベースや生産管理システムを活用したりする方法があります。あらゆる方向から生産データを分析することは、QCDの最適化を図るためには必須と言えるでしょう。
※PDCAサイクルとは
Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った、業務改善などを行うためのフレームワークです。「計画・実行・評価・改善」の4フェーズを繰り返し行うことで、持続的な改善が期待できます。また、各フェーズでの学びや経験を次のサイクルに生かすことで、効果的な改善を目指すことも可能です。業務改善だけでなく、品質向上や顧客満足度の向上といったシーンでも活用されています。
生産管理のよくある課題
自社の製品を需要や見込みに合わせ最適な状態で完成させるためには、さまざまな工程が必要です。内部および外部との連携も必須となるでしょう。複雑な生産管理業務においては、企業では以下のような課題がよく聞かれます。
- 全体的なスケジュールや各工程のスケジュールが把握できない
- リアルタイムな進捗状況が把握できず、納期に遅れが出る
- 生産計画と調整が複雑で、最適化できていない
- 在庫管理が難しく、適正在庫が確保できない
- 部品などの資材の誤発注がある
- 最適な人員配置ができず、コストがかかる
- 部署間の連携、情報共有が図れない
- 効率的なデータ管理が難しい
企業によっては、上記のような課題を複数抱えているケースもあります。特に、多品種少量生産を行っている場合は、生産体制の標準化が難しいと言えるでしょう。
このために「ヒューマンエラーが起きてしまう」「いつまでたっても計画を最適化できない」といった問題が発生しやすい傾向にあります。生産管理は生産業務の全体を管理するという性質上、担当者や生産管理部門だけではなかなか解決できないのが実情ではないでしょうか。
生産管理の効率化には「生産管理システム」の導入がおすすめ
上記のような課題の解決策として、「生産管理システム導入」を検討してみてはいかがでしょうか。各種課題の解決や、生産管理の効率化を図れます。
生産管理システムとは?MESとの違い
生産管理システムとは、受注管理や生産計画、購買管理や在庫管理など、生産管理におけるあらゆる業務を管理するシステムです。生産システムを活用することで、生産管理業務の負担を大幅に軽減できるでしょう。また上記に挙げた課題の解決や、業務の効率化を実現することも可能です。
生産管理システムと似たものとして「MES(Manufacturing Execution System):製造実行システム」があります。MESは「生産現場の実行管理」を行う、生産管理システムより狭域なシステムです。
具体的には、各工程と連携し効率よく製造することを目的としたもので、工程の把握や管理、作業者への指示や支援などを行います。双方の違いを理解し、自社に必要なシステムの導入を検討しましょう。
生産管理システム「ProAxis」導入のメリット
キッセイコムテックでは、生産管理システム「ProAxis」を開発・販売しています。ここでは、「ProAxis」の特徴についてご紹介します。
ProAxisについて
「ProAxis」は現場ニーズを重視した生産管理システムで、「適応性」「操作性」「柔軟性」を兼ね備えた、キッセイコムテックのオリジナル製品です。30年にわたる製薬メーカーの情報子会社としての経験と、数多くの製造業様へのシステム導入により培った業務ノウハウが生きています。
ProAxisの特徴
「ProAxis」は、受注生産または見込生産型の「量産」と、一品物を製造する「個別受注生産」の両方に対応しており、ムダのない調達計画と在庫管理が実現できます。また、シンプルなマスタ構成で現場でも使いやすい操作性を備えているので、実績データ収集や生産現場の可視化、品質データの集約による品質改善など、管理・運用がしやすいといった特徴もあります。
生産管理システムは、各企業の実務内容に合わせたカスタマイズが必要と考えますが、「ProAxis」は柔軟なカスタマイズ(アドオン)が可能なので、導入していただく企業に合わせたシステムを構築することが可能です。
すでに生産管理システムをご利用している企業もあるかと思いますが、生産管理システムの技術は日々進化しています。今の時代に則した最新のシステム導入を検討いただき、“レガシーシステム”からの脱却を試みてはいかがでしょうか。
ProAxisを導入するメリット
「ProAxis」の導入にあたっては、「安心のOne Stop Service」を謳っており、要件定義から本稼働まできちんと導く品質・進捗管理を徹底しています。本稼働後もお客様ごとに専用の保守問合せ窓口を用意し、万全なサポート体制を整えていますので、安心してお使いいただけます。
また、生産管理システムについては、Excelを活用しているという企業もあるかと思いますが、「ProAxis」なら、Excelではカバーしきれない問題が解決できます。
「量産」にも「個別受注」にも対応できる生産管理・債権債務管理システム「ProAxis」
生産管理の目的や仕事内容を理解して、効率化を目指そう
製造業の要とも言える生産管理は、業務内容が多岐にわたり、関わる人や部門も多いのが特徴です。非常に重要な業務であると同時に、課題に直面することも多く、生産管理の業務を遂行するためには、目的と仕事内容を正しく理解し、効率よく進めることが重要です。顧客の信頼と満足を得て、自社の利益アップのためにも、最適な生産管理システムを導入するなど、業務効率化を実現しましょう。


